日米合同委員会

「お金の話には直接関係ないですが…」
あわせて読みたい
戦後、GHQの占領政策を経て、
1960年(昭和35年)に締結された「日米地位協定」を
どのように運営していくかを協議する委員会が発足しました。
65年経った今もなお、継続しています。
協議は月2回行われ、どちらか一方の要請があれば、
いつでも会合できると、あります。
組織については、ウィキペディアから抜粋すると、
「日本側代表は外務省北米局長、アメリカ側代表は在日米軍司令部副司令官からなり、日本側は代表代理として法務省大臣官房長、農林水産省経営局長、防衛省地方協力局長、外務省北米参事官、財務省大臣官房審議官からなり、その下に10省庁の代表から25委員会が作られている。アメリカ側は代表代理として駐日アメリカ合衆国大使館公使、在日米軍司令部第五部長、在日米陸軍司令部参謀長、在日米空軍司令部副司令官、在日米海兵隊基地司令部参謀長からなる」
とあります。
ここでみなさんは、ひとつの疑問が湧きませんか!?
「双方とも政治家の名前がないのです」
委員会の分科会や部会などにも政治家の名前はありません。
事務レベルの協議とはいえ、国の重要な政策について、
政治家の参加はなく、合同委員会で合意すれば、
合意事項に一定の拘束力もあります。
問題点もあります。
・協議は非公開(召集も含め)
・国会への報告義務なし
・両国の了承がないと、議事録、合意事項は公表されない
国民から選ばれていない「官僚」が国の行く末を決めることが、
まかり通り、政治家も口や手を出せない。
両国間で何が協議され、決められているのでしょうか。
もはや「都市伝説」「陰謀論」「ポピュリズム」の話ではないですね。
私たちには関係ないでは済まされません。
みなさんも一度調べてみてください。
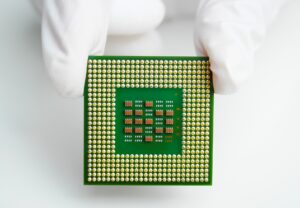

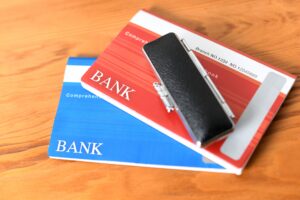




コメント