終活の現状

「人間誰しも訪れることです」
少子高齢化と言われて何十年も経っていますが、
いまだに活発な議論がされていない問題が「終活」です。
あわせて読みたい
2024年には高齢者3,600万人のうち三等親内の親族がいない人は、
286万人にのぼり、2050年にはその数が448万人に増えると推計されています。
「まだ遠い未来の話で、体調が悪くなくなってから、考えればいいのでは!?」
それでは終活までの一般的な経過を見てみることにしましょう。
徐々に心身に不安
>
大病を患い入院
>
介護施設入所(要介護認定)
>
心疾患で昏倒、入院
>
死亡
>
葬儀、納骨、法要
>
相続
個人差はありますが、この経過で言うと、意思能力のあり、なしが
重要なポイントとなってきます。
>介護施設入所の段階で、要介護認定が高くなると、
意思能力のない可能性も高くなってきますね。
2008年に全国紙やテレビで終活が取り上げられ、
エンディングノートへの注目が一気に高まりました。
それまでは「死」の話をするのがタブーとされていましたが、
団塊の世代が60歳を迎えて「個」の時代となり、
自身がどう生きたいか、どうありたいかをしっかりと考える人が
増えてきたことと関係していると思います。
国や地方自治体もようやく重い腰を上げ、
この終活の現状を踏まえ、対処するようになってきました。
しかしながら誰でもが受けられるサービスではないので、
民間事業者による「高齢者等終身サポート事業」が中心となってきます。
今年は、昭和で数えるとちょうど100年となります。
団塊の世代も後期高齢者(75歳以上)にさしかかった頃です。
親の終活から自身の終活へシフトチェンジしたと言えるでしょう。
「みなさんは終活についてどのようにお考えですか!?」


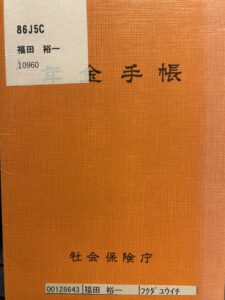




コメント