享保の改革

「暴れん坊将軍というよりも米将軍」
日本史の勉強で習いましたね笑
江戸中期、徳川8代将軍の徳川吉宗が、
幕府の財政を立て直すために行った改革です。
私自身、歴史の勉強が身になっていないのは、
誰がいつ、何をしただけではなく、
その結果、人々の暮らしがどうなったのかという考察が、
今ひとつ理解できていないところです。
猛省します。
徳川吉宗は、自ら指揮を執って庶民、幕閣に倹約を強いただけでなく、新田開拓、商品作物(しょうひんさくもつ:商品として販売するための作物)の栽培推奨によって農業を盛んにし、税収も増加させます。
とあります。
「令和の米不足」に照らし合わせると、
・質素倹約
・新田開拓
・商品作物の栽培推奨
どこか似ているところがありませんか。
現在の国政を担う政治家、官僚たちの「質素倹約」は、
全く当てはまっていませんが、国難であることは一緒ですね。
江戸時代の税収は年貢、つまり「お米」だったので、
お米の量だけでなく、価格の変動は、大きな問題でした。
今も昔も日本人のアイデンティティは「お米」です。
国の財政や経済に与える影響は計り知れません。
令和の米騒動で、「備蓄米」が世に出て、流通し、
価格が下がると思いきや、価格が安定しませんね。
いつの世もその影響を受けるのは一般庶民です。
付け焼き刃の政策など、解決には程遠いですね。
参院選前のパフォーマンスなど、必要ありません。
徳川幕府は、265年という長きにわたり、
「戦(いくさ)」なき時代をもたらせましたが、
「経済停滞」という問題も同時にもたらしました。
「令和の時代」はどうなるのでしょうか。

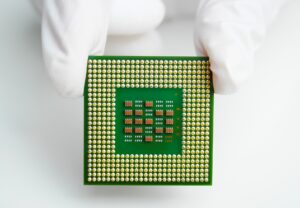

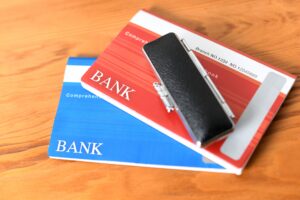




コメント